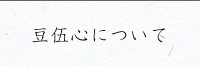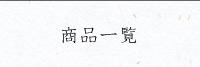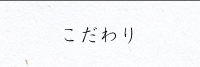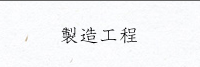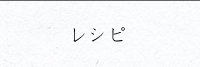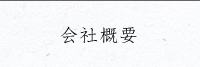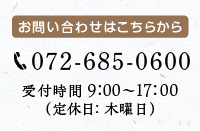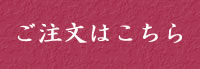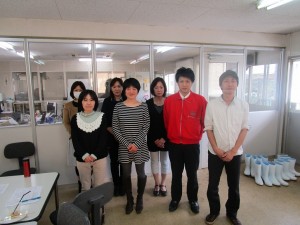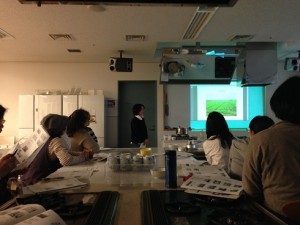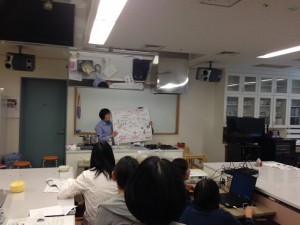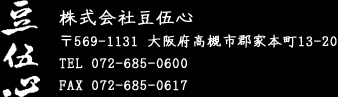生活クラブ生活協同組合大阪:大東四条畷地区:小川さん 小金井さん 盛林さんが弊社工場見学&勉強会を行いました。
スケジュール内容は①工場見学→製造工程&ライン見学(今回は絹ごし豆腐製造)とうすあげ体験②勉強会(事務所)→出来立て絹ごし豆腐試食・豆伍心について(生い立ち・名前の由来等)大豆について(竜王町稲作経営者研究会との取組等)・にがりについて(硫酸カルシウム・天然水にがりとの食べ比べ実験等)・製造工程について(市販品との違い等)③懇親会→豆伍心オリジナルお好み焼き・豆乳スープ・うす揚げとゆで卵マヨチーズ大葉和え
今回、製造はもちろんですが、特に豆伍心という生産者を知ってもらえれば色々な消費材を利用してみようかな?と感じてもらえればと思いながら学習会を行いました。今後も豆伍心から利用している方や新しい組合員の方には豆伍心の優位性を知ってもらい1つでも多く共感してもらえれば利用普及に繋がると考えています。最後に今回も小西主任(写真の男性)が居たので交流写真を頂きました(笑)近年、産直集会に彼が参加していますので今後とも宜しくお願い致します‼